七月の茶花
【7月の茶花】
うっとうしい梅雨の長雨もあがり、本格的な夏に入り、朝茶事、納涼釜などと、涼を求めた趣向の茶会が喜ばれる月です。
青竹の清きを切り、清き水を張り、清き心をもって、清き花を活けるという「四清同」の心をもって茶花を入れたいものです。


(紅額) (宗旦槿)
紅額は、あじさゐによく似ていますが、はじめ白色、次に淡紅色、最後に紅色になるのが特徴です。
底紅の槿は、千宗旦が好んだ故に、「宗旦槿」と言います。


(岩菲) (鷺草)
岩菲に縞芦を添えて、竹舟の花入れにいれてもよく似合いますね。岸部に繋いだ舟をイメージしてもいいですね。
鷺草を竹舟の花入れに入れて、水辺の生き生きとした夏らしい雰囲気を演出することも楽しいですね。


(半夏生) (唐松草)
半夏生の名前の由来は、「ハンゲシヨウ(半夏生)・夏至から11日目を半夏生といい、その頃に白い葉をつけることから。②ハンゲシヨウ(半化粧)・葉の一部が白くなり花よりも目立つので、化粧したように見えるから。」と、いうことです。


(銀梅草) (大葉擬宝殊)
銀梅草は、山沿いの木陰に生える多年草で、日本の特産種です。葉の先が2裂しているのが特徴です。
夏本番の季節には、涼しげな山野草が似合います。
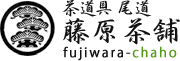


 (白沙山荘・羅漢さん)
(白沙山荘・羅漢さん)














