茶道表千家 深い味わい堪能
穏やかな心持ちに
尾道市中心部の商店街で、趣のある茶器を店頭に並べている老舗茶道具店「藤原茶舗」(尾道市土堂)を見つけ、のれんをくぐった。1913年創業という店の3代目店主、藤原唯恭(ただやす)さん(56)に茶器の由緒などを聞いていると、「茶道を体験してみてはいかが」と誘われた。戦国武将と茶道のかかわりを描いた山田芳裕さんの人気漫画「へうげもの」を読み、面白そうな世界だと感じていたこともあり、藤原さんが世話役を務める茶道・表千家流の研究グループ「松孤(しょうこ)会」の勉強会を訪ねた。(尾道通信部 石原敦之)
勉強会が開かれたのは、福山市沼隈町常石の市ぬまくま文化館「枝広邸」。10畳の茶室では、紺色の毛せんが敷かれ、メンバー6人がてきぱきと茶会の準備を進めていた。風炉(ふろ)釜からは湯が沸く音がかすかに聞こえている。
「まずは一服、味わってみましょうか」。着物姿の表千家教授、木曽絹子さん(83)=尾道市向島町=に従い、毛せんの上に正座して並んだ。勧められたアジサイをかたどった干菓子を食べて、早速、お茶を頂く作法を教わった。
茶わんを右手で取り、左の手のひらに置いた後、飲み口は正面を避けるため右手で2回に分けて、45度ほど右に回す。両手で包むように茶わんを持ち、三口半ほどで飲み、最後の一口は「ズズッ」と勢いよく吸い込む。口の中では抹茶の苦みが、先に食べた干菓子の甘みと溶け合って、ほんのりと優しい香りとなって広がり、幸せな気分になった。
飲み終わった後に、茶わんなどの道具を鑑賞するのも茶会の楽しみ方の一つ。茶会では、その日のテーマを掛け軸で表し、旬の花を生け、茶器や菓子にも季節感を取り入れるといい、木曽さんは、「茶会の場をどう演出しようかと考えるのも心が弾む」と教えてくれた。
茶道では、茶をたてた人への感謝や、次に待っている客への配慮などの礼儀が欠かせないが、ついつい忘れてしまい、隣に座った同教授、舛岡道子さん(66)=福山市山手町=に何度か指摘された。不格好に繰り返すうち、ようやく「最低限の礼儀と作法を知っていれば、どこの茶会に行っても楽しめますよ」と太鼓判を押してくれた。

最後にお点前に挑戦。茶わんに湯を注ぎ、抹茶を溶かすため茶せんを素早くかき回すと、「シャカシャカシャカッ」と心地良い音が静かな茶室に響いた。
作法を復習しながら、自らたてた茶を飲んだ。茶会の雰囲気に少し慣れたためか、自分でたてた茶のためか、より味わい深く感じられ、豊かな香りを堪能。ふと気付くと、日々の慌ただしさから離れて、穏やかな心持ちになっていた。
<メモ>茶道・表千家 茶人、千利休(1522~91)が大成させた茶の湯を受け継ぐ三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)の一つ。無駄を省き、閑寂、枯淡な趣の中に、「わび」「さび」と呼ばれる美意識を発展させた。江戸中期に町人などに広く支持され、家伝を継承する家元制度が確立された。茶道は明治維新(1868年)後は一時衰退したが、伝統文化や教養の一環として見直されている。
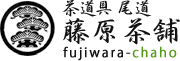


 (白沙山荘・羅漢さん)
(白沙山荘・羅漢さん)














